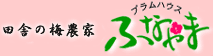|
|
12月上旬
8月中に干し上がった白干し梅をタルに詰め3ヶ月間寝かしました。8月下旬で紹介しました梅干しと見た目にはあまり変わらないのですが食べ比べてみるとはっきりと違い、すっぱいながらもまろやかな味になっています。これからはこの新梅干しをお届け致します。また、この白干し梅がふなやまの梅干し(味梅、かつお梅、しそ梅)の原点になります。 |

白干し梅(10kg) |

白干し梅 |
12月中旬
農作業11月上旬で紹介しました梅畑の土作りの一つとしてナギナタガヤ(イネ科作物)とプラムベッチ(つる科作物)の種を試験的に蒔いて見ました。これは梅畑の草生栽培(草を育て刈り取り堆肥にすること)を目的とする作業で梅畑の草生栽培にどの植物が適しているかを試験しています。去年はイタリアンライグタス(イネ科作物)を蒔き試験しました。
右の写真内の右側がプラムベッチが発芽した現在の状態です。左側が何も蒔いてない現在の状態です。 |

ナギナタガヤの種(左)とプラムベッチの種(右) |

プラムベッチ発芽 |
12月下旬
農作業9月上旬に紹介した南高梅の木です。このところの寒さと北風ですっかり落葉し、枯れ木のようになっています。しかしよく見ると花芽が大きくなってきました。これで5mm位あります、真中の1個は来春、枝になる葉芽で大きさは変っていませんので花芽の様子を9月と比べてみて下さい。開花予想ですが2月中旬になりそうです。 |

南高梅の木 |

花芽 |
|
 |
1月上旬
我がふなやま家では、兄弟親戚が帰省する正月に毎年餅つき大会を行います。これは、もち米を蒸しているところです。以前は我が家にも釜土がありましたが古くなり使えなくなってからは簡易の釜土を使っています。
また、当地方でも「うす」で餅つきをする家は少なくなりました。このうすは2代目で数年前に私が私有の山に入り欅(けやき)の木を切り出し、おじさんが得意の日曜大工でうすを作りました。普段は目にしないうすを使った餅つきに兄弟親戚も大喜びです。 |

もち米を蒸してます |

餅つき |
1月中旬
昨年中に梅苗の植え付け作業をしたかったのですが遅れてしまいました。南高梅の木は老木になると収量が減少するため老木を切り新しく苗の植え付けをします。これは昨年の農作業10月上旬の紹介と同様に一昨年の秋に南高梅を接木して、去年一年大切に育てた”南高梅の一年生”を梅畑に植え付けたところです。
植え付けた後、乾かないように敷きわらを行います。この南高梅の木は今後3年ほどで実が付き始め、一人前になるのは7〜8年後になります。また最近ではこの地方でも毎朝霜が降ります。大きくなってきた梅の花芽も霜に耐えています。 |

梅苗植え付け |

梅の花芽に降りた霜 |
1月下旬
農作業9月上旬、12月下旬と紹介しました南高梅の木です。これからこの木を剪定すれば、すべての梅の木の剪定作業を終了します。剪定された木の梅の発芽がますます大きくなってきました。そろそろ“つぼみ”に変わろうとしています。このころから農家の間では“花芽”から“つぼみ”に呼び方を変えます。開花まではもうちょっとです。ぜひ開花した時の梅畑を見せてあげたいです! |

剪定作業 |

梅の花芽
(1月23日) |
|
 |
2月上旬
先日、南高梅の花の受粉を助けるために養蜂業者さんからミツバチの巣を7郡お借りしました。梅畑の近くに置いたこの巣では女王蜂が一日に2,000個程度の卵を産み、常時3万〜4万匹のミツバチが働いています。その梅の花は、まだつぼみですが農作業1月下旬の紹介(上の写真)と比べるとますます大きくなり、中心に白い花びらが見え始めました。 |

ミツバチの巣 |

梅のつぼみ(2月3日) |
2月上旬
農作業2001年10月上旬で紹介しました接木の台木用南高梅の種を大切に保存していたところ梅の種が割れ始め、発根してきました。これを木箱に植え付け発芽するまで再び待ちます。また、先月より紹介してきました梅の成長写真ですが、いよいよ我が家の南高梅もきれいに咲き始めました。下の写真は2月上旬で紹介(上の写真)したつぼみが開花を始めたところです。 |

梅の種から発根 |

梅の開花(2月13日) |
2月下旬
農作業2001年11月上旬で紹介しました土壌分析の結果をもとに石灰肥料を施します。これは酸性化しつつある現代人の食生活を中和させるためにアルカリ性食品(梅干し)を食すように、南高梅の木もどれだけ良い肥料を施しても土壌が酸性化します。そこで石灰肥料を施し、梅畑を中和します。また先月より紹介してきました南高梅がついに満開になりました。 |

石灰肥料 施肥 |

南高梅 満開(2月23日) |
|